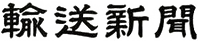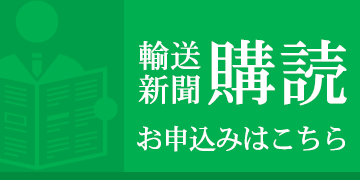貨物鉄道は不可欠な存在 札幌で第7回通運事業フォーラム 通運連盟
 フォーラムの模様
フォーラムの模様
全国通運連盟は1日、札幌市中央区の札幌グランドホテルとオンラインの併用で、第7回通運事業フォーラムを開催し、北海道経済の現状と貨物鉄道輸送、カーボンニュトラルの取り組みに関する2件の講演を聴講した。
冒頭あいさつした齋藤充会長は「北海道における貨物鉄道の維持・存続は、地域経済とインフラに関わる重要な問題。環境負荷軽減と安定輸送の観点から貨物鉄道は不可欠な存在であり、通運事業者としてもその役割を再認識し、地域と連携した持続可能な輸送体制の構築が求められている」との認識を示した。物流改正法やトラック適正化二法に関しても「物流の持続可能性と働き方改革を両立させるための政府の後押しであり、通運事業者も今後の業務のあり方を見直していかなければならない」と指摘。その上で「本フォーラムを通じて各改正法への対応や地域社会との共生、環境対策など、未来に向けた通運事業のあり方を皆さんと一緒に考えていきたい」と話し、フォーラムの意義を強調した。
記事全文は電子版から。